バブルに踊る「ワンレン・ボディコン」
一課担になって少し急いだ。ちょっと休もう。当時の世相は? 昭和天皇が逝去され、平成の世の中になった。何が変わって、何が変わっていないか。政権は相変わらず自民党が握っていた。小渕恵三官房長官(後の首相、故人)が「平成おじさん」と呼ばれた時の内閣は竹下内閣。平成元年(1989)4月にわが国で初めて消費税3%を導入したが、昭和の終わりに発覚したリクルート事件に多くの高官が連座していたため、6月に竹下内閣は総辞職した。この頃って、国民の声の高まりによって、内閣総辞職、というのはまあまああったんだなあ。昨年(2021年)10月4日に菅内閣も総辞職したっけ。これは、選挙対策だったな。
その後を継いだのが、宇野宗佑・第75代首相だったが、彼も女性スキャンダル「三つ指事件」で在職69日間という歴代在籍最短記録で辞職。次いで海部俊樹首相(故人)が第76代首相になった時代。世はバブル時代。本当に世の中にお金が有り余り、空前の好景気に酔っていた。
女性のファッションは「ワンレン・ボディコン」で、求める結婚相手は「三高(高学歴、高収入、高身長)」。夜な夜な、「ジュリアナ東京」や「マハラジャ」といったディスコで踊りまくり、高級外車を乗り回す「アッシー君」が迎えに来た。クリスマスイブには赤坂プリンスホテルや東京ベイヒルトンホテルなどの高級ホテルに宿泊してバカ騒ぎをするのがステイタスだった。馬鹿馬鹿しいが。大阪でも梅田付近にラジオシティ、アルファクラブ、デッセジェニーなどがあったらしい。全く行ったことないが。
そう言えば、このころのディスコブームは第二次とかで、第一次ブームは1970年代後半だそうだ。この頃、筆者は大学生だったので、京都にあったディスコにはよく行った。ディスコミュージックには乗れずに、チークタイムだけを狙っていた“壁族”だったが、ちっともモテなかった。

新地のラウンジでサツ官接待、でも自費で
そんな時代に、殺人事件やギョーカ事件を追いかけているのだから、超地味だ。それでも、たまに捜査一課の班長を接待するのは、大阪の高級繁華街・北新地のラウンジ。と言っても、クラブなどの高級な店には連れて行けないので、他社の記者と鉢合わせすることもあって慌てて店を変えることも、しょっちゅうだった。一つ誤解がありそうなので、断っておく。新聞記者に接待費はない。だから、すべて自腹だ。会社側は「そのために高い給料を払っている」と言う。全然、足らんけど。まあ要するに、社会全体が浮足立っていた。今から思うと、ホンマに馬鹿な時代だった。そのころを思い出させるものは、唯一、最近までクローゼットに釣ってあったダブルの背広だけだ。

ドタバタ「吉本」より泣き笑い「松竹」
スクラップを見ると、この年の5月21日に松竹新喜劇の大黒柱・昭和の喜劇王藤山寛美さんが60歳で亡くなっていた。これも、大阪のお笑いが大好きな身としては、非常にショックを受けた。ここで少し脇道に逸れるが、筆者の「お笑い人生」を。と言ってもお笑いの道に進んだのではなく、子供のころからのお笑いとの付き合い方だ。関西に生まれた子どもたちの“あるある”ではないだろうか?
神戸の下町に生まれた子にとって、お笑いへの向き合いは大切なことである。難しいことではなく、物心ついた時から松竹新喜劇と吉本新喜劇が存在していたため、極端に言えば、「吉本派」か「松竹派」かだ。関西のテレビ圏内にいる昭和30年代後半から40年代の子どもたちの土曜日は忙しかった。半ドンの授業が終わったら走って帰宅。お昼過ぎに始まる吉本を見なくてはならない。昭和40年代の初め頃は、吉本の後に「ローラーゲーム」というローラースケートのテレビがあり、確か午後3時頃から松竹新喜劇が放映されていた。吉本派から松竹派に変わったのは父の影響だった。
遊び人だった父は落語や喜劇に詳しく、筆者が幼いころから神戸の新開地や道頓堀に連れて行ってくれた。親父はいつも言っていた。「吉本の笑いはほんまもんやない。あれは単なるドタバタ劇や。おもろうて、やがて哀しきがほんまもんの笑いや。泣き笑いの松竹新喜劇がほんまもんや。寛美は天才や」と。小学校高学年になっても「吉本がおもろい」と言う友人たちに、口まねでこう言ったものだ。生意気なガキだったが、60代後半になって、その松竹の笑いが、寛美が妙に懐かしい。その6日後、“歌う映画スター第1号”の女優高峰三枝子さんが71歳で亡くなった。国鉄の「フルムーンキャンペーン」で上原謙さんと夫婦役で出ていたくらいしか知らないが。
冷戦終結 明るさあふれる時代に釜ヶ崎爆発
世界に目を移すと、冷戦がようやく終結に向かい、東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が壊れ、ソビエト連邦も崩壊に向かった。ゴルバチョフが民主化を進め、米ソの雪解けが進んだ。ドイツの東西統一も実現した。国内では、皇族のおめでた。当時の皇太子の弟秋篠宮に紀子さまが嫁がれた。なんとなく、世界も日本も一見、明るさに満ち満ちていた時代だったかな? 裏の世界は別として。

少しずつ、バブル景気が行き詰まりを見せ始めた平成2年秋だったかな? 大阪の火薬庫が爆発した。日雇い労働者が多く住む西成区釜ヶ崎、いわゆるあいりん地区だ。事の発端は、暴力団を担当していた西成署捜査4係の巡査長が、山口組系暴力団組長から現金230万円を受け取り、捜査情報を流していたことがわかり、10月2日夜に犯行を認める供述を始め、後日、収賄容疑で逮捕されたことだ。

この不祥事に抗議する日雇い労働者800人が西成署前に集結。制圧しようとする警官に投石したり、車や自転車に放火したりして、双方の数十人がけがをし、8人が公務執行妨害で検挙された。普段、警察に取り締まられる側としては、「ええ加減にせえよ!」「警察は信用できん」と言いたかったのだろう。この地区では、こうしたことがきっかけとなって、暴動騒ぎが度々起きていたが、この時は昭和48年(1973)以来16年ぶりだった。
暴動現場、記者もボコボコ
暴動騒ぎは治まらず、5日夜には群衆は1600人に膨れ上がった。日雇い労働者だけではなく地区外から集まって来た若者らも加わって、騒ぎはエスカレートした。当然、取材する側もチームを組んで何人かで取材しなければならない。市内回り6人全員が集められ、その「仕切り」として、一課担2人も現場に行った。暴動騒ぎの取材は怖い。暴徒化した労働者や若者たちは、記者を警官と同じ人種とみる。警官と同じように暴力を振るわれる。現に、産経新聞の一課担は騒ぎに巻き込まれ、ぼこぼこに殴られて入院したほどだ。読売新聞の市内回りの記者は西成署の屋上で取材中、投石を避けようとして足を挫いた。けが人に換算された。
こうしたチーム取材をする時には、現場近くに取材本部(ゲンポンと呼ぶ)を置く。たいてい、民家の一室を借りるが、この時は幸い近くに読売新聞の販売店があり、ここをゲンポンとした。筆者は幸いにもゲンポンキャップだ。ここから原稿を書いて、本社に吹き込んだり、FAXで送ったりする。幸い、そんなに現場に行かなくてもいい。怖いからなるべく現場に行かないようにしていたら、後輩の記者たちから「安富さん、怖いから来ないんだ。ずるいな!」と揶揄された。その時は否定したが、その通りだった。本来なら遊軍記者が現場に来なければならない。たまに差し入れに来るが、ゲンポンまでタクシーで来て直ぐに本社に帰る。わからないでもない。ある時、うちの記者が労働者らに囲まれた。そこに現れたのが、現場近くで生まれ育ったI記者。当時は警察回りではなかったが、心配だからパジャマ姿で現場に来たという。絡まれていた記者をかばって「おいおい、新聞記者さんに手荒い真似をしたら、あかんで」と地元住民のように凄んだという。労働者たちは立ち去った。I記者の武勇伝だ。暴動は数日後、やっと治まった。(つづく)
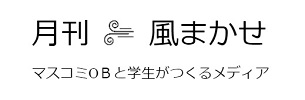
















コメント