夜な夜な飲んでタクシー帰宅
少し難しい話が続いたので、今回は軽い話題にしよう。当時の京都の飲み・遊び。
昭和60年(1985)頃、新聞社は元気だった。オール読売新聞は数年前に朝日から全国トップの座を奪い、1000万部獲得に向けて邁進していた。当然、給料は高く、前にも書いたが京都、神戸、大阪などのセット地区に転勤すると、20枚綴りのタクシーチケットを渡され、取材はほとんどタクシーで行った。取材と遊びの区別はつきにくく、飲んで帰る時はほとんどタクシー帰宅になる。

昭和60年当時の京都支局は御池木屋町にあったので、飲み屋街は目と鼻の先。高瀬川という風情のある小さな川を渡ると、喫茶「サボイ」、中華の「喜楽飯店」、高知皿鉢料理の「めん坊」、水炊きの「新三浦」が並んでいた。さぼりはサボイへ、宿直の晩ご飯は喜楽飯店、送別会はほとんどめん坊、OB会はちょっと高級な新三浦だった。喜楽の焼き飯は脂濃くて胸焼けしたが、新三浦の水炊きは絶品だった。先日、取材旅行に行ったが、サボイと喜楽は既になく、めん坊と新三浦は健在だった。

「軽く行くか?」スナック、ラウンジ…はしご酒
大学担当+遊軍だったので、夕方、支局に上がり、大きな事件や取材がなければ、たいてい夜7時半を過ぎると、夜の街に繰り出す。新聞記者は必ず「軽く行くか」と丸めた指を口に持って行き、誰かを誘う。決して「軽く」で済まないのだが。それでも、“短駆”と“長駆”があった。短駆の時は、先ほどの支局周辺の高瀬川沿いの店へ。当時、よく行ったのが、メキシコ料理の店で、テキーラという強い酒を飲んで、マスターのギター演奏を楽しんだものだ。マスターは「パンチョ」と名乗っていた。
長駆となると、木屋町を下って行く。今でも健在の高瀬川の東側にある、近藤正臣の実家で有名なおばんざいの店「お料理めなみ」や、西側にあった大衆居酒屋「よしみ」(残念ながら昨年廃業した)、鴨川右岸にある中華の「珉珉」などによく行った。お腹がふくれると、今度は木屋町から先斗町を下り、スナックやラウンジへ繰り出し、カラオケに興じる。もっと調子が出ると、先斗町を抜けて左折、鴨川を渡ると、祇園だ! といっても「一見さんお断り」で高級なお茶屋さんなどには新聞記者の給料では行けない。まあ、ここでもスナックかラウンジだった。


時には、タクシー数台で山科区にあるラーメンの名店「夜鳴きや」や銀閣寺近くのラーメン屋「中華そば・ますたに」、皿うどん・ちゃんぽん専門店「まつお」などにも遠征した。
もてもてデスク「ネクタイ50本、女房に切られたぁ」
斎藤デスクに連れて行ってもらうと、高い店になった。安い中華や居酒屋は素通りで、めなみか祇園のお茶屋関連の店だ。ここで、説教を受ける。司法+遊軍のNさんや、綾部通信部のMさん、舞鶴通信部のHさんらがよく一緒だった。斎藤デスクの社会部時代の話、学生運動にのめり込んでいた同志社時代の話、文学や政治の話、様々だった。しかし、この席で言われた言葉を今も覚えている。「安富君は基本的な教養というものを具えていないね」。「えっ、NさんやM、Hさんは具えていますか」と問うと、「そうだね」と言われた。ショックだった。高校時代から推理小説に嵌まったのが、まずかったか。新聞記者になってから、ノンフィクションを読むようにしていたが、「お里」が知れたようだ。
まあ、それでも斎藤デスクは気に入ってくれていたようで、随分、飲みに連れてもらった。愚痴も聞いた。少し、プライバシーに触れることになるが、敢えて。斎藤デスクは女性にもてた。なんでだろうか? 決して男前ではないが、モテた。雰囲気があったのだろう。ある日、飲んだ席で珍しく愚痴った。「ネクタイ50本、女房に切られちゃったぁ」。絞り出すような掠れた声で。これ以上は書かない。新聞記者は女性好きな人が多い。筆者もだが。
行政回りや遊軍は比較的早くから飲みに出られるが、サツ回りは夜回りがあるので出足が遅い。深夜10時や11時過ぎから合流する。よく行ったのが祇園のスナック。後に、京都支局の“大事件”の主人公となる先輩のNさんとはよく行った。井上陽水の妻・石川セリの「ムーンライトサーファー」が十八番だった。筆者は相変わらず松田聖子や中森明菜を歌っていた。「ピンクのモーツアルト」とか「サザン・ウインド」とか。
合流してきた松ちゃんとMさんは、共にサザンオールスターズを得意にしており、松ちゃんは「真夏の果実」、Mさんは「メロディ」を熱唱した。毎晩のように深夜1時過ぎまで飲み歌い、金払いは良かったから、みんなモテた。NHKや朝日、産経、京都新聞の記者たちともよく一緒になり、呉越同舟の祇園で騒いだ。
後輩に首絞められ「無実や!」と叫んだ
ある日の未明、いつものように、タクシーに相乗りして帰宅していた。この夜はスナックの後、「もう一軒行こう」と沖縄料理の牛テールスープが美味しい店に行った。府警回りの藤原キャップ、松ちゃん、N川さんと4人。この店の売りが、アルコール度90度以上の泡盛「どなん」。この酒を飲むのが漢気だった。飲むのではない、大きく口を開けて流し込まないと喉の奥が焼けた。それを何杯か流し込む。酩酊状態になる。
洛西ニュータウン組の3人は最後。一番先に降りるN川さんのアパートが近づいてきた河原町三条を上がった辺りだった。下車したN川さんが筆者をタクシーから引きずり下ろして倒し、道路の真ん中で首を絞めた。何か叫んでいるが、聞き取れない。どうやら、彼が好意を寄せていた支局のパンチャーさんに、筆者がちょっかいをかけていると邪推したようだ。「無実や!」と叫んだが、なかなか緩めてくれない。やっと藤原キャップと松ちゃんが引き離してくれたが、首周りに痣が残った。
翌日、冷静になった彼と話し、誤解は解けた。実は、その彼女に独身の同期の記者を紹介しようとしたが、同期がドタキャンしたため、仕方なく数日前に2人で飲みに行った。それが気に食わなかったらしい。彼と彼女はその後、めでたく結婚した。
日航機事故 犠牲者の顔写真集め
酒絡みの失敗話は、山ほどある。それは、統合版という田舎の支局からセット版という本社近くの総支局に来たことによる、文化の違いもあるのだが。特に、休みの日に大きな事件が起きた時の対応だ。地方支局では人数が少ないので、当然、大事件の時は全員出動だが、所帯の大きな総支局では大丈夫やないか?という甘えが生じる。
昭和60年8月12日もそうだった。盆休みで実家の神戸に行き、近くの居酒屋で父と飲んでいた。妻は出産直後で島根の実家にいた。飲みながら店のテレビを見ていた。午後7時過ぎだった。ニュース速報で「日航機消息を絶つ!」と流れた。羽田空港を6時過ぎに離陸し、大阪伊丹空港着の予定だった日本航空123便が消息を絶ったというのだ。あの日航機墜落事故だ。この事故については、後にじっくりと触れるが、この後の筆者の行動に、斎藤デスクから大目玉を食らったのだ。
要するに、大事故の発生を知りながら、筆者は父と飲み続けて、その夜は実家に泊まり、翌日京都支局に出勤した。もちろん、支局に連絡は入れたのだが、バタバタしていたのか、連絡が上手く伝わらなかったようだ。支局は大騒ぎだった。日曜日の夜、東京から大阪方面に帰る乗客がほとんどで、京都の関係者も多かった。筆者が担当してた大学の関係者もたくさんおられた。顔写真を入手しなければならない。散々叱られた後、ボトボトと大学関係者や企業を回り、顔写真を何枚か取った。
大きな教訓となった。いやならなかったのかな? その後も同じようなことをやらかしたから。
「君は社会部では生きていけないな」
昭和61年の1月3日に古都税に反対する男が金閣寺に立て籠もった。この日も妻の実家、島根県松江市で妻と6か月になった娘といた。元日から2日にかけて松ちゃんと2人で泊まり勤務をして、3日から正月休みだった。車で実家に到着して風呂から上がると、ニュース速報が流れた。
「やばい!」。すぐに支局に電話した。優しいFデスクが出た。「安富君、今、島根にいるそうです」。支局長に報告してるんだろう。Fさんは言った。「今日はいいよ。明日ゆっくり帰っておいで」。翌日、おっとり刀で支局に駆け付けると、斎藤デスクがまたもや言い放った。「君は社会部では生きていけないな」。
21年ぶり阪神優勝 読売だけど虎ファン感涙
この年、一番うれしい出来事は、阪神タイガースの21年ぶりのリーグ優勝、初の日本シリーズ制覇だ。読売新聞にいて何で阪神ファン? 不思議に思われる方も多いだろう。読売巨人軍は読売グループの一員で関連会社だ。当時は「読売興業株式会社」が経営する球団で、この会社は西部本社も同時に経営しており、一時は西部本社の赤字を巨人軍の黒字で賄っていたという(平成14年から株式会社読売巨人軍)。当然、グループ社員はほとんどが巨人ファンだ。しかし、大阪読売だけは違った。表に出しているだけでタイガースファンは3割いた。“隠れ”を入れるともっといたかもしれない。

京都支局にも筆者をはじめ熱烈な虎ファンが4、5人いた。松ちゃん、Nさん、写真部のTさんらだ。優勝した瞬間は今も脳裏に残っている。Tさんがいる写真部の小さな部屋で熱烈なファンらが押しかけて、その時を待っていた。中西清起投手が投げ、ヤクルトの選手が打った。ピッチャーゴロだ。日本列島が揺れた。大阪ミナミの道頓堀川に飛び込む若者たち。支局の虎ファンらも抱き合って泣いた。巨人ファンのT支局長や斎藤デスクはしらけていたが。
テーマは「京都駅」50回15万字の大連載


色々あった転勤1年目もあと1か月足らずになった頃に、またまた斎藤デスクのご下命が出た。今度は新年からの京都版での連載だった。タイトルは決まっていた。「京都駅 建都千二百年へ」。京都駅に纏わる様々な出来事を物語風に語るという1年間の連載だった。毎週1回で50回以上は続く。それを基本的には1人でやれ、という。やりがいはあったが、なかなか荷が重い。
連載記事は掲載日の少なくとも3、4日前には出来上がっていなければならない。それを1年間、続けるのだから、200行×50回=1万行=15万字だ。かなりの分量なので、それなりの取材時間も必要だ。ほとんど、生活のほとんどをこの記事取材・執筆に取られる。
取材に入る前に、大まかなコンテを作る。事前にそれなりのエピソードを調べておく必要がある。京都駅と関係する人生模様を少なくとも20人くらいはピックアップしなければならなかった。
1回目は、当時の京都府知事で後の参議院議員の林田悠起夫さん(故人)。小学校6年生の時に初めて、今の綾部市から京都に来た時の様子を書いた作文から入り、やがて三高(現京都大学)に進学。東京大学法学部に進み、海軍を経て後に蜷川共産府政から保守府政に変わった京都府の知事になった。その人生の節目には必ず、京都駅の思い出があるというストーリー。「激動昭和まっしぐら」「望郷と決意と 不正に新ルール」。これもかなり、斎藤節がさく裂している。
2回目は、故稲畑勝太郎氏(実業家での政治家、稲畑産業の創業者)。明治10年11月15日の早朝、稲畑氏ら8人の少年たちが京都駅1番ホームから旅立ち、フランスに織物、染色などの分野で技術の習得に励んだという物語。タイトルは「少年たちの1番ホーム」だ。3回目は、「国鉄生みの親」と言われる故谷暘卿氏の「遥かなレール」。しんどくて長い連載取材が続いた。(つづく)
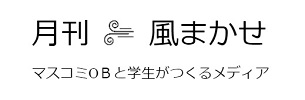



















コメント