
本作を、惹句にあるとおり「いまだかつてないドキュメンタリー映画」にしているのは、「はなし」で構成した点である。タイトルでもその点が強調されているが、本作は「はなし」の群れでできている。さまざまな人々が語る「はなし」の群れがどっと押し寄せてきて、200分を超える長尺ながら引きこまれて見た。「いまだかつてない」本作の非凡さとはどういう点か、そこにどんな希望があるのだろうか。
輝きも不気味もある「はなし」の群れ
なにより見るべき非凡さは、人々の「はなし」で構成したことだ。ここには大まかに言って3種の「はなし」がある。(1)部落差別を被ること、つまり被差別についての「はなし」とその闘いの「はなし」、(2)闘いの向かう先となる側の「はなし」、(3)歴史に関する学問的解明の「はなし」の3種である。事実や実態、歴史を動かないもの、否定しようのないものとし、「これが正しい」「真実はここにある」といった提示の仕方はされていない。つまり、最後に(3)の内容を示して結論とするというつくりにはなっていない。どれも「はなし」として全編を構成している。これはなかなかに非凡なことだ。差別の不当性をなにほどかは理解し、被差別への共感をもちたい、差別に加担しないようにしたいと思う者でも、事実や実態、歴史はこう、そのシステムはこうと、「正しさ」や「真実」を岩のように不動のものとして示されると、あとは黙るしかなくなってしまう。
ところが本作では、部落史研究の黒川みどりの本質を衝いた鋭く深い考察や指摘も、黒川の「はなし」として並べられている。上記で述べた(3)である。一般的には、ドキュメンタリーのつくりはまず実態を見せて、その不当性を示してから、研究者が登場してそれらの不合理性を言うといったものだ。学問の言説はレヴェルの違う「正しさ」や「真理」として使うというのが、テレビ・ドキュメンタリーなどでよく見る構成である。研究者の「はなし」という扱いではドキュメンタリーは成立しないと思われている。もちろん本作での黒川の「はなし」は、「はなし」だからといって正しさを感じさせないわけではない。むしろ「はなし」だからこそその内容に耳を傾け、結果として「聞けるはなし」としてなるほどと腑に落ちる。小さな黒板に黒川が板書しながらの「はなし」にした絵づくりも、学問言説を「はなし」として並べるための効果をあげていて、監督の構成力を見せている。
闘いの文化

見るべき非凡さの2点めが、闘いの有理性を、組織的正義として整理して示すのではなく、担った当事者たちの「はなし」の群れとして並べていることだ。上記で私が(1)とした、被差別の経験と解放闘争に関する「はなし」である。「被差別の当事者」という括りを絶対とするのは誤りであり、危険でもあるのは承知している。承知のうえでやはり、彼らの「はなし」の具体性と、理念の普遍性には特段の輝きがある。京都、三重、大阪で、行政に要求を出し、司法に訴え、映画を自主製作しといった闘いの経験に立つ「はなし」を聞いて、私は中上健次とは違うことを思った。中上健次は、部落も天皇も文化的産物だからどうしようもないという旨の発言をしたと本作で言及されている。文化は政治闘争によっては変えようがないという意味のようだが、「差別という文化」に対峙してきた「闘いの文化」という文化をなぜ見ないと、私は思ったのだ。
豊かな「闘いの文化」は、ここにある多くの「当事者のはなし」のなかに息づいている。とりわけ私が魅了されたはなし手が、80代の高橋のぶ子である。10代で結婚して京都崇仁地区に住むようになった高橋による、ユーモアを交えての「はなし」は、闘いで培った確かな観察眼と仲間への堅固な信頼を伝えている。これを「闘いの文化」と呼ぶなら、その継続や積みあげは、抑圧に対する単なるリアクションに終始することとは決定的に違う。「闘いの文化」が無用になって忘却されるのを理想としていると、いつか新種の抑圧が発生したときに対抗する手段も力ももたない脆弱で残酷な社会をまたぞろ招来するだけだろう。そんなことを思いながら私は、カメラの前で堂々と眠る高橋のかまえない豪胆さに見惚れていた。
監督の「はなし」

本作を非凡にしている3点めとして挙げておきたいのが、監督である満若勇咲の成長記録になっていることだ。満若はインタビュアーとしては登場するが、映画のなかで「はなし手」として話すわけではない。本作製作の経緯は、プレス資料にある彼の文章に詳しい。満若は、大学卒業時に屠場を取材して製作した『にくのひと』(2007年)の劇場公開を断念せざるを得なくなったことを、はっきり失敗と捉えた。その苦い失敗を踏まえて成長し、失敗の責任を果たそうとしている。満若が「15年前の自分に向けて作った作品」(プレス資料19頁)と言うように、製作の動機とそこに至る歴史は本作でわかる。前作の何がダメかを明確に批判する人の「はなし」を入れただけではない。惜しくも早世されたが、前作の公開が頓挫したあとも支えてくれた加古川食肉産業協同組合理事長の中尾政国が登場して「はなし」をしている。むろん本作はすぐれて社会的なドキュメンタリーだが、同時に監督個人の私的ドキュメンタリーでもある。20代前半に勢いよく撮った作品で躓いた青年が映像のプロとして15年の経験を積んで、わかる、見える、感じられるようになった、ごく私的な感触も併せもつ点が魅力的だ。満若自身の「私のはなし」も本作にある「はなし」の群れのなかのひとつである。
質問してみたいこと
いろんな「はなし」を聞いて、是非とも質問してみたいことが2つある。1つは、黒川みどりの「はなし」のなかで言われる、天皇制をなくせば部落差別がなくなるとはならないという旨の発言について。黒川が言うのは、板書内容も併せて考えるとおそらく、次のような論理だろう。つまり天皇制というフィクショナルな制度を支える貴賤の象徴システムのもとでは、個人が圧殺されて同調を強要する社会になるので、現今の天皇制をなくしたところで卑賤をつくりだすことはやまない。そのとおりだと思うのだが、では戸籍制度をなくせばどうなのかと尋ねてみたくなった。社会運動目標として、天皇制廃止よりも具体的で、かつ日本社会がなかなか手放さないできた貴賤の象徴システムを機能停止に追いこむ可能性をもつのではと思う。
もう1つの質問は、鳥取ループ/示現舎の主宰者、宮部龍彦に向けたものだ。2007年の作品の件以来、部落問題から距離を置いていた満若に本作の製作を決意させたのが『全国部落調査』復刻事件(2016年)だという。復刻出版し、「部落探訪」と称する動画を撮影、公開するYou Tuberである宮部その人を登場させたのは、ドキュメンタリー監督、満若の功績である。被差別部落について矛盾した「はなし」を得々と語る宮部の不気味さは、実はそう奇矯なものではなく、日本社会の不気味さである。そう考えると、是非とも宮部に質問してみたいことがある――『全国部落調査』復刻、旧地名と新地名の対照リスト公開などでどれくらい儲かっているのか。まずは需要があったはずで、復刻出版や地名のネット公開などでさらに需要を増幅させたに違いない。そうした需要が、この人物にどれほどの利益をもたらしているのか。この質問に宮部はどんな顔でどう答えるだろう。需要の問題はこの人物の不徳や不正義というだけではすまないからこそ、裁判にもなった。支える社会があり、求められているからこその復刻出版だろう。
不気味な凡庸
宮部を登場させたことにはいろんな意見があるだろう。発言の機会を与えるべきでない、部落差別の再生産になる、そういう意見にも一定の正しさがある。それでも私たちが、宮部だけでなく、上記で(2)とした「はなし」の不気味さを直視しなければならないのはまちがいない。たとえば、覆面で語る60代の女性が、「血の穢れ」を理由に結婚しない、させないとみずからの部落差別を披歴している。揺るぎない自信で断定的に話しているのに顔を出さない。「部落の人」とのつきあいがあり、本心を知られたくないからだと言う。この人物は「血の穢れ」を本気で忌避しながらそれを隠し、平然と日常のつきあいを続けている。実に不気味だ。しかしそこにこそ日本社会の凡庸がある。そんな不気味な社会の凡庸にどう対峙するか――これは、205分にわたって種々の「はなし」を聞いた私に向けられた質問である。(敬称略)
はぎわら・ひろこ 大阪府立大学名誉教授
「働く女性の人権センター」の機関誌『いこ☆る』で映画評論を担当して17年になる
[東京]ユーロスペース
[大阪] 第七藝術劇場、シネマート心斎橋
[京都]京都シネマ、京都みなみ会館 ほか全国の映画館で順次公開。
公式HP:https://buraku-hanashi.jp/
ツイッター:https://twitter.com/buraku_hanashi
フェイスブック:https://www.facebook.com/buraku.hanashi
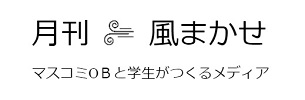









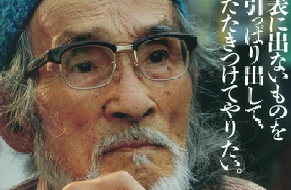








コメント