11月のグアム国際映画祭で最優秀ドキュメンタリー賞と観客賞をダブル受賞し、海外でも評価が高まっているドキュメンタリー映画「くじらびと」について、石川梵監督の撮影秘話をここ3年間、事あるごとにうかがう機会に恵まれている。その都度、「撮影の過程でそんなことまであったのか」と思わされる驚愕エピソードの目白押しで、改めて監督の制作への執念を知る。梵さんは不測の事態に陥った時に備え、志を引き継ぐ者への遺書まで用意していたのだという。そして、聞けば聞くほど「くじらびと」は最新機器が汎用化されたデジタル時代だからこそこの世に産み出された作品であり、「どうやって撮ったの?」と我々に問いかけてくるのだ。
銛1本で鯨に挑む伝統の漁

梵さんはインドネシア東部に位置するレンバダ島に30年間も通い続けて、母なる地球(ほし)の生命をいただくことの尊さを我々に教えてくれた。
海と森に囲まれたわずかな居住地に敬虔なカトリック教徒が住むラマレラ村。毎年5~8月、漁師たちが沖合のサブ海に乗り出し、マッコウクジラ漁を行う。人口1500人ほどの小さな漁村で400年間も続けられて来た伝統の営み。必要な分だけの狩りを行う、21世紀のわれわれが直面しなくてはならない持続可能な漁でもある。
小さな木造の舟で近づき、一本の銛(もり)で挑む巨大動物との闘いで、帰らぬ人となった漁師も少なくない。この漁の実態に迫ろうと、これまで多くの外国人研究者や英BBCのような報道機関が村を訪れたが、それは通訳を介しての取材であり、限界があった。これでは村人の心のひだに触れることはできない。痛感した梵さんは公用語のインドネシア語だけでなく、文字のない現地のラマレラ語も覚え、積極的に村人とコミュニケーションを行った。
村人に溶け込み「懐かしい風景」描く

一つ一つのシーンに、村人と心が通じ合い、お互いを受け入れ合う「ラポール」状態であったことがにじみ出ている。無邪気に遊ぶ子供たち。それを優しそうに見つめる母親のまなざし。そして、教会で真摯に無事を祈る姿と愛する者を失った深い悲しみ…。梵さんがクジラを狩る決定的瞬間を撮ることができたのも、日本から数千キロも離れたこの村で、毎日、かけがえのない時を刻んだからだ。梵さんはそんなラマレラ村の暮らしを「現代人が失った、懐かしい日本の風景」とも描写した。
梵さんは捕鯨の決定的瞬間を収めることができなければ、この映画の撮影を終えるつもりはなかった。しかし、ありとあらゆる撮影機材を用意し、一日10時間以上も大海原にいるのに、捕獲どころか、クジラさえ現れない日々が続く。「ボンがくるとクジラが取れない」―。信心深い漁師たちは梵さんにこう恨み節を漏らすこともあった。
クジラを取らなければ、村で待つ家族を養うことができない。それは梵さんにとっても同じだった。決定的瞬間を撮らなければ、日本に帰れない。クラウドファンディングでなんとか撮影資金を集めたものの、残されたチャンスがどんどん失われていく。
自分が不測の事態に巻き込まれ、もうラマレラにも来れないかもしれない。追い詰められていく中で「この映画を完成させないと死ねない。(自分に何かあっても引き継げるよう)遺書まで書いた」と振り返る。
後日、梵さんに改めて直接、聞いたら、「この映画は時代を超えて残る自信があった。撮影が危険なことはもちろんですが、それよりも飛行機が落ちるとか、何があるか世の中、わかりませんから」と話してくれた。
帰国前日、命がけで撮った奇跡の映像

そして、2019年夏、滞在日を延長して翌日にはもう帰国するとなった最後の日、ついにクジラと対決する場面に遭遇した。主人公として追っていた一人のラマファ(鯨捕りの漁師)が海に飛び込み、一番銛を入れた。命の灯が消える中で必死になって抵抗するマッコウクジラ。船上で叫び合う男たち。格闘で波しぶきが上がって空に舞う。逃げるために必死のクジラは大きな体を舟に打ち付けてきて、一瞬、梵さんは海に投げ出された。
ここまで来て水泡に帰すわけにはいかない。絶対に逃すわけにはいかない。梵さんはなんとかアウトドア用小型カメラ「Gopro(ゴープロ)」のスティックを口にくわえて泳いで渡り、違う船に移った。
海に落ちたらクジラに引きずり込まれる。奈落の底へ沈む。あえてそんな命知らずのことをする者はラマレラでもいない。格闘は数時間にも及んだ。この日を千秋の思いで待ち望んでいた梵さんはありとあらゆる場面を想定し、頭の中で撮影のシミュレーションをしていた。ドローンを飛ばして俯瞰する映像を取り、鮮明な血で染まる海の中に飛び込んで、死にゆくクジラの目を撮った。たった一人で、上空・船上・海中の3場面の捕鯨の営みをそつなくこなした。
「奇跡としか言いようがない。神様は何というドラマを用意していたのだろう。世界を驚かす映像が撮れた」
ドローン、GoPro……最新機器が活躍

この作品には高性能の最新撮影機器が威力を発揮している。もし、ドローンがなかったら、もし、汎用されたGoProがここまで持ち運びしやすく映像が鮮明でなかったら、くじらびとのあの映像は生まれなかった。
想像力たくましく近未来の撮影手法も考えてみた。もしテクノロジーの発展が10年早く撮影時の2019年夏に来ていたら、61歳でありながらデジタル時代の寵児である梵さんはさらなる高性能機器を用意していたに違いない。船員一人ひとりに小さなウェラブルカメラを身につけての撮影に臨んでいただろう。漁師の小さなつぶやきや銛をつく音さえマイクに拾うことが可能だっただろう。
長時間撮影可能となり、さらに軽量化したドローンは搭載されたサーモグラフィーセンサーを頼りに、縦横無尽に大海原を動き回るクジラの生態を克明に捉えだろう。そして、梵さんは水中にさえAIが自動操縦するカメラを投げ込み、クジラの最後の瞬間を可視化することに成功しただろう……
地球で生きる意義、現代人に伝える
そんなことを想像しながら劇場版を見終わろうとしたとき、恥ずかしながら、私は最後のシーンで涙した。青い海をバックに流れるあの透明なメロディーを聞きながら、梵さんは地球で生きることの意義をエンディングにしたためたのだと思った。
いつも映画情報が満載な梵さんのフェイスブックページ。ある時「#酔っ払い映画監督」と題して梵さんがこんなメッセージを流した。友人としこたま飲んだ時に、思いついたことをスマホで打ち込んだに違いない。
「『くじらびと』は究極の『いただきます』映画で、『生きることの本質をとらえている』とよく言われるが、ひと言で言えば『喝!』なのだ。だらだら生きる現代人に向けての『喝!』なのだ」
カーボンゼロ革命が進む中で、今、私たちが何をすべきなのか? 「くじらびと」を見て、大自然と共存するラマレラからの喝!をぜひ味わってほしいと切に願う。
佐々木 正明 ジャーナリスト、大和大学社会学部教授 1971年岩手県生まれ。大阪外国語大学(現・大阪大学外国語学部)卒業後、産経新聞社に入社、 大阪社会部、モスクワ支局長、リオデジャネイロ支局長、運動部次長、社会部次長を歴任。 特派員として五輪・パラリンピックやサッカーW杯を取材した。 2021年春から現職。著書に『恐怖の環境テロリスト』(新潮新書)、『シー・シェパードの正体』(扶桑社新書)
「くじらびと」公式ホームページ https://lastwhaler.com/
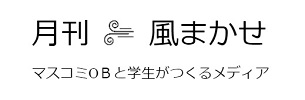

 「くじらびと」公式ホームページ
「くじらびと」公式ホームページ 








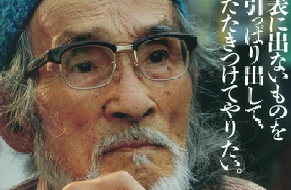








コメント