目を覚ませ! 大阪社会部!
筆者は全くタッチしていない事件「おなかの赤ちゃんが助けてくれた」を追い続けている。書きながら何度も涙が零れた。そして、思う。読売大阪社会部には骨があった。なぜ今、弱い人の味方になる記事が大阪の紙面に載らないのだろうか。そんなケースは目の前にたくさんあるはずだ。例えば、6月に射殺された安倍晋三元首相の数々の疑惑の中で明白な罪の一つ森友学園事件で、元首相の妻昭恵氏らの関与が記されていた公文書を何か所も改ざんさせられた近畿財務局の赤木俊夫さんの自殺の真相になぜ迫らないのだろう? 統一教会と癒着する国会議員たちをなぜ追及しないのだろう? 獣医学部が創設された加計学園のその後はどうなっているのか? いやもっと身近な子供たちの貧困問題をなぜ取り上げないのだろうか? そんな矜持を持つ新聞記者が今の大阪読売社会部にはいないのか! 現場は東京ではない。大阪社会部の管内で起きているのだ。情けなくて仕方ない! 目を覚ませ! 大阪社会部!
栄転したネコババ事件主犯格と対面
年甲斐もなく熱くなってしまった。本論に戻ろう。ところで、上海列車事故の最中に大阪府警が「警察官ネコババ事件」を発表し、筆者が上海の取材を済ませて帰国した際、持ち場の曽根崎署に“珍客”がいた、と書いたが、それは、この堺南署の事件の関係者がいたからである。ネコババ事件の当事者、いやある意味で主犯格だった谷口寿一・堺南署副署長が曽根崎署副署長に栄転していたのである。4月末に帰国して挨拶に行った時、谷口副署長は赴任していた。愛想は良いが何となく腹に一物ある人物だな、というのが第一印象だった。時が過ぎ次々と真実が明らかになるに従って般若のような表情に変わっていったのをよく覚えている。5月末に谷口副署長は処分が出て警務部付になるのだが、1か月近く曽根崎署の副署長として付き合わせていただいた。ずっと、読売の悪口を言っていた。
出頭求め刑事来訪「首を賭けても間違いない」
連載は続いた。次第に、この事件は単なる一警察官の拾得物横領事件ではなく、署ぐるみの「冤罪でっち上げ事件」に姿を変えていた。というより、本当の姿が見えて来た。連載は丁寧に冷徹に事件の「素顔」をあぶり出す。
2月9日夕方、堺南署からみち子さんに呼び出しがかかり、みち子さんは隣の泉ケ丘派出所に出向く。刑事と女性警察官がおり、刑事は「いつ結婚したのか。いつ槇塚台に来たのか。その日、奥さんは朝から何をしてたか」などとまるで犯人扱いで聴く。『供述調書』と書いた用紙にカーボン紙を敷いていたので、みち子さんは「何か私が犯人みたいですね」と刑事に聞いた。「わしも事件やったら強く言えるんやが」とごまかしたという。午後9時過ぎ1時間余りの質問攻めから解放された。
3日後の2月12日午後、「事件は解決した」と言って刑事が来た。みち子さんは留守だったので、夫の清治さんは「てっきり、派出署員が着服してまして」と告げられると喜んで槇塚台派出所に向かった。ところが。部長刑事は3,4㎝角の白っぽい封筒の切れ端3枚が入ったビニール袋を見せて「これ、見たらわかるやろ」と言う。「わからんな」と言う清治さんに、「お宅の敷地内から出て来たんや。10日の休みの日に捜した。そこまで言うたらわかるやろ。(奥さんが派出所へ)持って行ったところを見た人がいるんやけど、その時間帯には警察官おらんかったという証言がある」と言う。いよいよ、みち子さんの犯行と押し付けて来た瞬間である。清治さんは強く否定し、帰宅して、みち子さんに「警察はお前が犯人やと言うて来た」と伝えた。みち子さんは「そんなもん警察で正直に言えば通るもんでしょ」とまだ深刻には受け止めていなかった。しかし、事態がのっぴきならないことになったと感じた清治さんは、みち子さんの父や叔父たちに来てもらった。そこへ、若い刑事がみち子さんの出頭を求めて来た。12日午後5時過ぎ、店の土間で刑事と対決となった。みち子さんの父が部長刑事に「もしも犯人と違うたら名誉棄損で訴える」と言えば、部長刑事は「17年の刑事生活がある。首を賭けても間違いない」と見栄を切ったという。しかし、逮捕状は出てなかったので、部長刑事たちは帰った。

恐ろしいことだ。当に逮捕寸前だった。親戚たちが同席して、皆で刑事たちを追い返したから良かったものの、任意同行に応じていたら、自白を強要されていたことは確実だろうし、ひょっとしたら嘘の自供をさせられていたかもしれない。この事件の「闇」が如実に現れた瞬間だった。このビニール袋に入った銀行の封筒の切れ端とみられるものは、後に明確に拾得された銀行封筒とは別ものだったことが判明し、みち子さんを派出所で見たという“目撃証言”も否定された。要するに完全にでっち上げだったのである。
幹部の栄転直前、不祥事もみ消しはかった?
当時、署長、副署長、警ら課長の堺南署幹部3人はその春の人事異動で栄転が内定していた。そこに降って沸いた「拾得金蒸発事件」だった。派出所員の横領の可能性が誰かの頭に浮かんだのは間違いない。出世を前にややこしい事件はもみ消してしまえ。主婦を犯人としてしまえば、世間にわからずに処理できる、と考えたに違いない。関係者が明確な供述をしておらず、大阪府警の監察も追及が不十分だったので真相は明らかではない。しかし、筆者も当時取材に当たった中山さんも、冤罪でっち上げの確信犯だ、と信じている。中山さんはこのネット連載を読んで、「とても照れくさい限りです。でも、今思えばよく書いたな、とも。新聞記者をしていてほんとによかったなとも思います」と感想メールを返してくれた。
中山記者は悩んだ。警察が全面否定していることを書けるだろうか? 社会部のデスクに相談するまで1週間近く、抱えていた。しかし、みち子さんの無実を信じていた中山記者は、上司の堺支局長Mさんに相談する。Mさんは開口一番「おもろいな、早書けや」と言った。そして、原稿を書き始めた中山記者をM支局長は車で本社に送り、その日の社会部の当番デスクの河井洋次長(故人)に相談した。「直ぐに行こう(出稿しよう)」となり、河井次長からの深夜の猛攻撃に遭う。夜11時の出稿を目指して、細かい詰めの質問が嵐のように浴びせかけられた。特に2つ3つ、なかなか詰め切れない質問に遭い、「もう1回、調べ直せ!」と何度も怒鳴られたという。「わからないことは『わからない』としか言われへんのやけど、怖かったなあ」。しかし、13版セット地区からの社会面トップ記事には全く直しがなく載った。河井次長は一課担、府警キャップを歴任した大阪社会部レジェンドの一人で、ジャーナリスト大谷昭宏さん原作の漫画「こちら大阪社会部」では、主人公の厳しくも優しい先輩記者として描かれている。筆者は数回しか原稿を見てもらっていないが、怖くて厳しいデスクだった。河井次長と筆者のわずかなエピソードは後にしよう。
「あんたを首にするぐらい簡単や」と署長。クロや!と確信
河井次長の確かなデスクワークに加え、紙面掲載の翌日から大阪府警幹部と対峙することになる当時のA府警キャップも本社に呼ばれた。中山さんは言う。「河井さんは前府警キャップやけど、一度も原稿を止めなかった。A府警キャップも大丈夫か?と聞くだけで、止めなかった。あの頃の社会部やなあ!と今では思うね」。M支局長も司法担当のベテラン記者だが、だれもやめとけとは言わなかったという。深夜にコメントを求めた井上正雄・堺南署長はこう言った。「待ってくれ。あんたとこの府警の連中には知り合いがようけおる。あんたを首にするぐらい簡単や」。中山記者はこの時、確信した。「クロやな」。
『おなかの赤ちゃんが助けてくれた』連載22回
中山記者は3月15日に府庁担当に異動したが、6月初め、加茂紀夫・社会部次長(当時)から呼び出された。「警官ネコババ事件を連載する。タイトルは『おなかの赤ちゃんが助けてくれた』や。君はもちろん、連載の中心や」。取材班には2年後輩のF井遊軍記者と入社2年目の女性M記者が入った。F井記者は大阪読売社会部の名文記者の一人、後に、府警サブキャップ、社会部次長、地方部長と、筆者は大変お世話になるのだが、あまり気性は合わなかった。M記者とも何度か取材を共にした。とにかく、1週間足らずの準備期間を経て連載は始まった。5月25日にみち子さん側が大阪府警(大阪府)を相手に200万円の慰謝料支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした際に、10月半ばに出産予定のみち子さんはこう言った。「この子がおなかにいなければ、逮捕されていたかもしれません。この子が助けてくれたような気がして……。ひどいでしょう。こんな不当な捜査は許せません」。連載のタイトルには、弱いものを守れなかった大阪社会部の自戒が込められていたに違いない。連載は7月7日まで22回に及んだ。
証人捏造、自白強要……事実関係争わず「認諾」 府警が全面敗北
7月15日、国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁論で府警側は、証人捏造やニセの証拠によってみち子さんを犯人に仕立て上げようとし、自白を強要したことなどの事実関係について全く争わず、訴えを認諾した。全面的な敗北を認めた。T副署長は曾根崎署副署長から警務部付となった。連載は、その年の日本新聞協会賞を受賞した。

しかし、わずか30秒での「認諾」に不満を募らせる具足さん夫妻。
認諾で事件の詳細が封じ込まれた。
権力側が「認諾」をすることによって、原告側が求めている真相解明のための過程が削がれてしまう。最近もどこかで聞いたような国家権力の逃げ方だ。いずれにしても、警察権力が一主婦を、そのメンツから冤罪に陥れる事件は、気丈な夫妻のがんばりと新聞記者の執念によって暴かれることとなった。中山さんは今、改めて振り返って言う。「普通なら(記事書くのを)やめるよ。面倒やもん。特ダネ書いたけど、ちっとも嬉しくなかった。連載は夕刊だったから、統合版(地方)の読者は一日遅れの朝刊で読んでいた。夕刊は月曜から土曜までだが、統合版読者には月曜日は読めない。そしたら、『圧力がかかったんと違うか!』と読者から抗議が来た。それだけ、期待がかかっていたんやね。同時に警察からの圧力に新聞は屈するのでは?という思いもあった。だから、大変な連載やった。連載記事を見た加茂さんも原稿にうるさい人でね。新聞協会賞はおまけやけどね。新聞社に対する信頼感と不信感がまだあった時代やね。新聞社側にも余裕があったわな。今の若い記者たちを見てたら、人は少ないし、忙しいからかわいそうやと思うわ。でもなあ……」。(つづく)
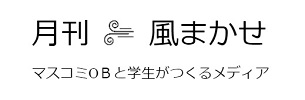

















コメント